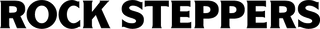【レビュー】Topo Athletic Traverse / 1000km超えの登山使用から見えた“実際の用途”
はじめに
Topo Athleticのハイキングシューズ「Traverse」。その見た目はトレイルランニングシューズ的でありながら、設計思想はあくまで“歩くこと”に重点を置いています。
筆者はこのTraverseを2024年2月より使用開始し、近所の裏山から六甲山、八ヶ岳、北アルプス、時には舗装路も含めて合計1000km以上を歩いてきました。さらに「大シガイチ(滋賀一周トレイル)」挑戦でも2足目を投入し、160kmのロングトレイルを行動しています。
この記事では、その長期間の使用経験をもとに、Traverseのメリット・デメリットをレビューしていきます。これからTraverseの購入を検討している方にとって、製品理解の一助となれば幸いです。
TOPO ATHLETICというブランドについて
TOPO ATHLETIC(トポアスレチック)は、アメリカの元Vibram USA社長だったTony Postによって創設されたフットウェアブランドです。"Move Better. Naturally."(より自然に、よりよく動く)というコンセプトのもと、ランナーやハイカーにとって自然な動きを促すシューズ作りを続けています。
トポの最大の特徴は、足指の自然な広がりをサポートするワイドトゥボックスと、ドロップ差(つま先と踵の高低差)が少ないロープロファイルな構造。走るためだけではなく、「人間が自然の中をどう快適に移動できるか」を追求したブランドだと言えるでしょう。
Traverseというシューズについて
Traverseは、Topoが「ハイキングを主眼に開発されたトレイルランニングシューズととハイキングシューズのハイブリッド」として開発したモデル。軽量なトレランシューズと、堅牢なハイキングシューズの中間に位置するシューズです。
- ソール厚:約30mm
- ドロップ差:5mm
- ソール素材:Vibram® Megagrip + ロックプレート
- アッパー:エンジニアードメッシュ
アウトソールは非常に滑りにくいコンパウンドを使用していることと、ミッドソールが硬めに設定されていることもあり、未舗装路や岩場でもしっかりとした接地感を保っています。また舗装路や林道歩きも苦にしない、バランスの取れたシューズに仕上がっています。
筆者の足とサイズ選び
筆者の足は、実寸26.5cm。幅はやや広めで甲は高くありません。Traverseでは27.5cmを選択し、夏場の靴下はあえて薄手のものを使用しています。
中厚〜厚手ソックスが推奨されがちな登山シューズですが、筆者は夏場の発汗や靴内の蒸れによるトラブルを軽減するために、薄手ソックスへ移行。結果として、足裏のトラブル(マメやふやけ、スレなど)が激減しました。
ただし、靴ずれのリスクがゼロではなく、靴紐の締め方や足との相性を見極めることが重要です。また、時期によっては中厚手のソックスの方が快適な場合もあります。そのあたりは季節だけでなく行動量にもよります。自分は行動量、時間が多いのであえて薄手にしています。
使用したフィールドとコンディション
筆者はTraverseを以下のような環境で使用してきました:
- 標高1500m以下の里山や中低山。一般登山道で使用。六甲山、生駒山、滋賀や九州の山々など、泥・岩・火山性ザレ場が混在する地形。
- 森林限界を越える高山帯。八ヶ岳や北アルプスなど、森林帯から岩稜帯、稜線までを歩く一般登山道で使用。一般登山道を含む縦走路での使用。八ヶ岳や北アルプスなど、森林帯から岩稜帯、稜線上までを歩行。
舗装路や林道など歩きやすい道では、適度なクッション性が活き、逆に不整地では安定性とグリップ力が効果を発揮。ある程度どんな場所にも対応でき、「ストレスが溜まらない」ことこそが、長期使用の中で最も重要な性能だと感じています。

Traverseの安定性について:厚底でも“ぐらつかない”理由
「安定性」という言葉は非常に曖昧ですが、ここでは「足元がグラつかず、意図せず足裏のバランスを崩さないこと」と定義します。
人がもっとも安定するのは裸足の状態です。足と地面の間に何も介在しない状態であり、厚みや柔らかさが存在しないことで、重心がブレず、前後左右どの方向にも倒れにくくなります。対して、シューズのソールが高くなればなるほど、柔らかくなればなるほど、設置時の安定性は低下します。これはバランスボールのように、足元が動く構造になることで、重心や足首がブレやすくなるためです。
近年のトレイルランニングシューズでは、この不安定さを補うためにソールの接地面を外側に広げ、台形のような形状を取ることで、左右への倒れ込みを防ぐ設計が一般的です。
一方でTraverseは、ソール厚は約30mmとやや厚めながらも、ソールは垂直に落ちる形状が採用されています。ミッドソールがやや硬めに設計されており、ソールを外側に広げる必要がないためです。。その結果、必要なクッション性を持ちながらもブレが少なく、足裏の接地感覚も比較的保たれています。
動的な場面でも、ソールの剛性と構造が安定性を支えており、「厚底でありながらグラつきにくい」という状態が実現されています。これは前述の通り、ソールの高さや柔らかさに伴う不安定さを、ミッドソールの硬さで制御しているためです。安定性とは単に硬いかどうかではなく、“いかにブレを抑えるか”という設計思想において、Traverseは非常に合理的で完成度の高いシューズだと感じます。
厚底=不安定、と思われがちですが、Traverseは30mmという厚みながらソールの硬度がやや高く、かつソール形状が台形ではなく垂直に落ちているため、接地感に違和感がありません。
台形ソールは広い接地面で安定性を生む一方で、細かな凹凸に対して誤差が生じやすく、意図しない障害物を踏んでしまうことで足首やかかとにストレスがかかることもあります。Traverseはむしろ「設置面のミスを起こしにくい」ソール形状で、足裏感覚を大事にするユーザーには好まれると思います。
歩けるが、走りにくい。あくまで登山シューズとして
Traverseは走れないわけではありません。しかし、走ることを目的としたときに明確な“違和感”があります。
- ソールの屈曲がやや硬く、テンポが出にくい
- ロッカー構造が弱めで、重心移動のサポートが少ない
- 他のトレランシューズと比べて重量がやや重い
このため、「スピードハイク」や「山を走りたい」ユーザーには不向き。一方で、しっかり歩く登山においては、硬すぎず、柔らかすぎない絶妙なバランスが快適さを生みます。
耐久性と摩耗:1000kmを超えてなお使える状態
Traverseを長期使用して感じた耐久性は“おおむね良好”です。大きな破れやパーツの剥がれは起きておらず、アッパーの堅牢さにも満足しています。
筆者が2足目を使用したのは、「大シガイチ」という非常に長距離の挑戦を一気に行動する必要があり、靴が途中で壊れるリスクを回避したかったためであり、1足目に明確な不具合があったわけではありません。実際、1足目も現在も引き続き登山で問題なく使用できています。
アウトソールのラグ(凹凸部分)は使用に伴って摩耗しますが、それはMegagripソールのラバーコンパウンドの性質によるものであり、単にラグのパターンや高さで評価すべきではありません。摩耗は見られるものの、グリップ性能自体に大きな不満はなく、濡れた岩場や泥道でも滑ることなく動ける場面が多く、信頼できるコンパウンドだと感じています。
ただし、森林限界を超えるような岩稜帯で使用すると、アッパー素材の消耗が早まる可能性がある点には注意が必要です。Traverseは軽量性を優先した設計のため、堅牢性が高い素材は使用されていません。3点支持が必要になるような場面でも使用は可能ですが、スピードや快適さを求める一方で、寿命は縮まりやすいと感じています。
逆に、岩場の少ないトレイルや林道などでは、こういったシューズの方が圧倒的に快適に歩けることも多く、行動のスタイルに合わせて選ぶことが重要です。
Traverseはどんな状況に向いているか?
Traverseは、概ねどんな登山道でも歩きやすい部類のシューズだと思います。もちろん、無雪期かつ一般登山道を歩くという前提です。
よく「初心者向け」や「中級者向け」といった表現が使われますが、登山のレベルを単純に区分することは難しく、そういった分け方でおすすめ・非推奨を判断するのは現実的ではないと感じています。それよりも、「どんな地形で」「どんな目的で」歩くかによって評価が分かれるべきだと思います。
向いているのは、整備の行き届いた登山道です。軽快に歩くことができ、Traverseの特性がよく活かされます。
逆に向いていないのは、トレランスタイルのシューズ全般に共通する点でもありますが、3点支持が必要になるような岩場です。そういった環境では、登りも下りも、どちらかといえば使いづらさを感じます。ただし、一般登山道というのは、シューズの性能で登れる・登れないが決まるほどシビアなルートではないため、どちらかと言えば、シューズよりもクライミング技術や基本動作の方が重要になると考えます。
また、岩稜帯ではシューズへのダメージが大きくなります。特に、スピードを出さずにゆっくりと登る場合は、堅牢な登山靴(たとえばスポルティバのようなモデル)を履いた方が無難で、結果的にコストパフォーマンスが良いことも多いと思います。
とはいえ、岩稜帯を含むルートでも、スピードを重視する山行ではこのTraverseを選ぶことが多いのですが。
向いている状況
- 整備された登山道や縦走路をテンポよく歩きたいとき
- 長時間行動を前提としたロングトレイルやファストパッキング
-
重装備ではない状況で、快適性を優先したいとき
向いていない状況
- 岩稜帯が多く、アッパーに強いダメージがかかる行程
- 耐久性を最重視したいハードユースや重荷での行動
- 高速でのトレイルランニングを想定している場合
類似モデルとの比較:MERRELL Agility Peak 5
Traverseと使用感が近いモデルとして、MERRELLのAgility Peak 5があります。筆者はAgility Peak 5でも数百km以上を走り、歩いた経験があり、両者の共通点と違いを実感しています。
まず前提として、Agility Peak 5は長距離向けのトレイルランニングシューズです。ただし、その設計には「スピードよりも安定性を重視した要素」が多く含まれており、結果的に“速く走るためのシューズ”というよりも、“長時間を安定して走り/歩けるシューズ”としての性格が色濃く出ています。
ソールは柔らかさの中にもある程度の剛性があり、接地時に脚へのストレスを感じにくく、長時間の行動でもぶれにくい構造です。また、アウトソールにはVibram Megagripが採用されており、加えて「トラクションラグ」と呼ばれるラグの突起構造が、濡れたトレイルや滑りやすい地形でのグリップ性能を高めています。実際にTraverseと同じようなコンディションで比較したとき、Agility Peak 5の方が滑りにくさを感じる場面がありました。
アッパーに関しては、つま先から側面にかけて補強が厚く施されており、足まわり全体がラバーで包まれている構造になっています。この設計によって、多少の水に強く、耐久性への信頼感が高まっているのは確かです。TraverseよりもAgility Peak 5はややタフ寄りの設計と言えるでしょう。

大シガイチ後半の280kmはこのシューズで歩いた。
走ることを前提としたシューズでありながら、歩く場面でもストレスが少なく、重量も過度ではないため、「歩く/走るの中間」的なシチュエーションにもよくなじむシューズです。Traverseとの違いを簡単に整理すると以下のようになります:
- クッション性は似ているが、Agility Peak 5の方がやや柔らかく、やや厚底
- 走るための設計ではあるが、安定感もあるため長距離歩行にも十分使える
- アウトソールはグリップ力・耐久性ともに優秀で、Traverseよりも滑りにくさを感じる場面がある
- アッパーの補強がしっかりしており、耐久性が高い
-
Traverseが“歩くことに特化したランニング的な靴”とすれば、Agility Peak 5は“走れるけど歩きにも強いトレランシューズ”
筆者としては、Traverseは「安定性と接地感」を、Agility Peak 5は「快適さと耐久性のバランス」を重視しているように感じており、目的や山行スタイルに応じて選ぶべきシューズだと思っています。
おわりに
Traverseは、トレランシューズのような軽やかさを持ちつつ、歩行時の安定感もしっかり備えた一足です。整備された一般登山道では快適かつ軽快に歩くことができ、長時間の縦走にも向いています。
一方で、森林限界を超えるような岩稜帯では、アッパー素材の特性上、破れやすさや摩耗の早さといった弱点もあります。そういった環境で使用する場合は、シューズの寿命が縮むことを前提に、それでもスピードや軽快さを重視したい場面で使うのが現実的です。
重要なのは、登山者の経験値ではなく、「どんな山を、どんな目的で歩くか」。Traverseは、その判断軸に応じて「快適性」と「耐久性」のバランスを使い分けることができるモデルだと感じています。
すべてをカバーする万能な靴ではありませんが、自分の足と山行スタイルに向き合うことで、その良さが引き出されるシューズです。
大切なのは、どんな山をどんな目的で歩くのか。その山行スタイルにTraverseが合っていれば、きっと心強い相棒になってくれるはずです。