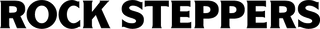大峯奥駈道 無泊縦走 2025年5月
目次
- はじめに:なぜこの道を選んだか
- 無泊チャレンジというスタイルについて
- 道のりと印象に残ったシーン(前半)
- 道のりと印象に残ったシーン(中盤)
- 道のりと印象に残ったシーン(後半)
- 大峯奥駈道の「厳しさ」と「感動」
- 装備と補給の工夫(前半)
- 装備と補給の工夫(後半)
- この道を歩こうとする人へ
はじめに:なぜこの道を選んだか
世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部であり、多くの人にとっては一般的な登山道とは異なる、特別な道だと感じられるはずだ。単なる登山ではなく、「修行の道」としての特異性と神秘性を備えている。道としての厳しさ、雄大な自然、そして山の奥深さ。そのすべてに魅かれ、いつかは踏破したいと常に思っていた。
コースとしては距離約100km、累積標高約8,000m。
無泊チャレンジというスタイルについて
一般的には5泊6日が標準とされるこの工程を、なぜ無泊で挑戦しようと思ったのか。実のところ、自分でもはっきりとした理由があるわけではない。ただ、僕が大好きなYouTubeチャンネル「アカコンスポーツ」の影響が大きいかもしれない。無泊縦走に挑んだ記録映像が残されており、その動画はぜひ一見の価値がある。
挑戦できるだけの体力と気力は、自分にはあると思っている。そして、神秘的で深い山々に対する畏敬の念。自分の身体と心がどこまで応えてくれるのか。その二つが入り混じったような感覚だ。トレランレースのようにスピードを競っているような感覚とは、まったくの別物だ。
また、無泊での縦走に挑戦している人たちは、皆一様に格好良い。多くがランナーでもありながら、単に速さだけではない、どんな状況でも自己完結できる強さを備えているように思う。彼らの持つ強さは、競技としての「速さ」とは別のベクトルにある格好良さだ。その強さに、少しでも近づきたいと願っている。 どれだけ早く進めたかではなく、この道を歩いたという体験そのものが、かけがえのない価値なのだと思う。大峯奥駈道に限らず、深い山で無理をすることにはリスクがある。だからこそ、余裕を持って歩くことが何よりも大切だ。
ある時、2025年は大峯奥駈道を無泊縦走したいと、飲みながらOさんと話していた時に、過去にOさんもチャレンジして失敗したという話になった。予定を合わせてチャレンジしようという流れになった。
道のりと印象に残ったシーン(前半)
天気予報は雨。2日前には警報級の大雨になるという報道もあり、状況次第では近場の山に行くプランに変更しようかとも考えていた。だが、徐々に予報が変化し、前線の位置も予想より東に進んでいたため、豪雨の可能性は低くなった。

そこで、予定通り出発することを決断。ただし、出発時刻を早め、天候が悪化した場合に備えて停滞や撤退の余地があるよう、時間的な余裕を持たせた。 夜19時30分、出発。雨は降っている。レインウェアを上下とも着込み、缶コーヒーでカフェインを体に入れてスタート。吉野駅からしばらくは舗装道路を歩く。
車とすれ違ったとき、ヘッドランプに照らされた運転手の表情は訝しげだった。こんな時間に、しかも雨の中で山に向かっているのだから当然だ。雨は止まないが、それほど強くはない。予報どおりで、むしろ想定より穏やかだった。この調子なら問題なく進めそうだ。
登山道に入ってからは、しばらく気持ちよく登っていく。しかし、下りの路面は雨で非常に滑りやすくなっていた。軽い装備で、前傾姿勢のまま着地した瞬間に足を離すような走り方をすれば、滑りやすい道でも転倒せずに進むことができる。普段はそのやり方で対応している。ただ、今回歩いているのは大峯奥駈道だ。距離も長く、岩や石の質感も里山とは違う。木の根の太さもまったく異なる。装備も最低限に絞っているとはいえ、それなりの重量だ。雨の下りでは足へのダメージが蓄積しやすいため、足幅を狭くして、負担を最小限に抑えながら進んだ。

歩き始めて4時間半ほどで、五番関の女人結界門に到着。それから間もなく雨脚が強まった。風もかなり強い。同行していたOさんは短パン姿で、当然ながら「寒い寒い」と震えていた。洞辻茶屋で着替えと補給を行う。自分も汗で濡れたベースレイヤーを脱ぎ、アルファダイレクトのフーディに着替えた。改めて感じたが、アルファダイレクトは本当に優秀な素材だ。濡れた体を温めてくれるのに、蒸れることがない。アクティブインサレーションは、今の時代の登山において必携といってもいいのではないか。

道のりと印象に残ったシーン(中盤)
このあともしばらく雨が強く、登山道には水が流れ、まるで小さな沢のようになっていた。そうこうしているうちに朝を迎える。空にはまだ雲が残っていたが、雨は止んでいた。予報どおりだ。気温も上がってきたため、レインウェアの上だけを脱いで行動を続けた。

大普賢岳に近づくにつれ、鎖場や崖の縁を通るような場面が増えてきた。体力だけでなく、神経も使うセクションだ。ようやく弥山小屋に到着し、久しぶりに温かいものを口にすることができた。さらに、ありがたいことにノンアルコールビールも販売されていた。もちろん飲酒はできないが、このタイミングでのノンアルは心に染みる。十分すぎる感動をもらえた。


ここでレインパンツを脱ぎ、靴下も交換。足の裏と足指のケアは、この先を進むうえで非常に重要だ。 その後、複数の鎖場や難所を越え、釈迦ヶ岳で釈迦像に手を合わせる。さらに進んで深仙宿に到着する頃には、同行していたOさんの様子に変化が見え始めていた。腰の痛みを訴え、弱気な発言も増えていた。どうやら、心の中でエスケープを視野に入れ始めていたようだ。

進むのか、撤退するのか、判断すべきタイミングは今だった。南奥駈道に入ってしまえば、エスケープは極めて困難になる。普段は冗談ばかり言い合う仲だが、このときばかりは真剣だった。時間的余裕も決してあるとは言えない。進むなら今、撤退するならこの小屋でビバークするしかない。葛藤があったはずだが、Oさんは「進む」と決断した。 しかしその後、普段なら問題ないような下りで転倒してしまう。腰も相当痛そうだった。日も暮れ、ヘッドランプを灯しての行動となる。足元のリスクは一層高まっていた。

下り斜面に大きな岩が埋まっており、雨で濡れ、苔もついている。自分はその岩を避けて脇道に迂回したが、Oさんはそのまま岩に足を乗せて進もうとしていた。 「危ない!」と声をかけ、回避してもらう。普段のOさんなら、迷わず判断できるはずの場面だった。経験も脚力もある人だ。それだけ限界に近づいていたのだと思う。 そして、平治宿で「進めない」と判断された。完全に動けなくなったわけではないが、このまま進めばルート上で限界を迎えるリスクが高い。そうなる前に、ここで撤退を決めるという選択だった。夜はこの宿で休み、翌朝、難所を避けた比較的安全なルートで下山し、バスに乗る計画を立てた。
他の人なら一緒に下山したかもしれないが、Oさんはそれを一番嫌がるタイプだ。基本は自己完結型で、必要なときだけお互いに協力するというスタンス。限界を迎える前に撤退を選べる冷静さもある。エスケープ後の道のりは長いが、ほとんどが舗装路だ。問題ない。だからこそ、進むなら自分も早く決断しなければならなかった。安全を確認し合い、自分は先へ進むことにした。
道のりと印象に残ったシーン(後半)
単独行となってから、闇夜の中を進む。よく考えれば、これは自分にとっていつものスタイルに戻っただけだ。怖さよりも、危険を避けるために神経を研ぎ澄ませて集中する。鎖場や崩落地、崖の縁など、特別な技術は必要ないものの、疲労がある状態では万が一のリスクを想像してしまう。たとえば、疲れた中、鎖場で三点支持を保っているときに無駄な力が入り攣ってしまえば重大な事故につながる。そうならないよう、集中を切らさずに進む。基本的なクライミング技術が身についていれば、こうしたリスクはある程度避けられる。

これまでの工程で時間の余裕はあまりなくなっている。できるだけペースを上げ、走れるところは走る。明け方6時を過ぎたころ、ようやく玉置神社に到着。何とか時間的余裕を確保できた。あとは本宮を目指すだけだ。
玉置神社周辺には参拝者の姿があり、下界に降りてきたような気持ちになる。その安心感からか、気が緩んでしまったのか、ここからの道のりが今回最もつらく感じられた。標高も低く、人の気配もある。それでも、この道もまた修験道であり、小さなアップダウンが何度も続く。気温も上がっていて暑い。眠気はなかったが、幻覚がひどくなっていた。

10km以上歩いたと思っても、実際には5kmも進んでいない。2時間歩いたつもりが、まだ1時間も経っていない。だが、明るい時間の幻覚は、不思議と楽しい。遠くの枯れ木や岩が人や動物に見え、しかもそれらが動いているように見える。ぼんやりとではなく、はっきりと人の姿に見えるのだ。近づいてようやく幻覚だったと気づく。何度も幻覚を見るうちに、それがむしろ面白くなってきた。「次は誰が見えるのか」「本当は何が見えているのか」と想像してしまう。

軍用テントでキャンプをしている幻覚が見えた。これはさすがに幻覚ではないだろうと思ったが、近づいてみるとやはり幻覚だった。当然だ。ただ、あまりにもリアルで、人がいないだけで焚き火台までしっかり見えていたのは印象的だった。
一番驚いたのは、子どもがいる幻覚だった。10歳くらいの子と幼児がいて、まさかと思いながら近づくと、何と自分の娘たちがそこにいた。ママごとのような遊びをしていて、笑いながら動いている。そんなはずはないと頭では分かっている。でも、どう見ても娘たちにしか見えない。至近距離まで近づいて、ようやくそれが倒れた木だと分かった。
そんな状態でも、歩いていればいつかは着く。時間の余裕もあったので、焦らず進み続ける。ついに熊野川が視界に入る場所まで来た。本宮も見える。あと少しだ。幻覚はまだ続いていたが、怖さはなく、優しい幻覚ばかりだった。むしろ楽しめるくらいだった。

ついに熊野川に辿り着いた。だが、熊野川は昨日の雨でダムの放水をしていた。どうやっても渡ることができなかった。迂回して、熊野本宮大社へ向かう。無事に辿り着いた。やり切った。最初に探したのはビールだった。ようやく飲んだビールは美味しかったが、いつものように身体には入っていかない。売店でパンとアイスクリームを買い、バスに乗って帰路についた。

結果的に時間としては40時間半ほどかかった。雨もすごい時間もあったが、風が最後まできつかった。雨でペースが上がらなかったこともあり、余裕があったからか行動食は下記。
柿の種1000kcal、ピーナッツ200kcal、ビスケット100kcal、バームクーヘン200kcal、マナバー1/2個100kcal、カップ麺400kcal、チキンラーメン380kcal、サタケパスタ200kcal、コーラ45kcalくらい。トータル2600kcalちょっと。なんだか行動量と計算合わなないが、これだけしか食べていないので大量の行動食があまりました。
大峯奥駈道の「厳しさ」と「感動」
技術的な難易度以上に、精神的な厳しさを感じる場面が多かった。一般的な登山道や観光登山とはまったく異なり、登山者を突き放すような、試されているような感覚があった。特に単独になってからは、風が強く、景色は曇りと霧で覆われて何も見えない。ただただ歩く。その時間に「修行」という言葉が腑に落ちた。
一方で、ルート自体は丁寧にマーキングされており、地図を見なくても進めてしまう。だからこそ、確実な場所でも気が緩みがちになる。疲れているときほど、分岐などでは必ず地図を確認する必要がある。慢心は命取りだ。 奥深い山中を歩き続けるなかで、自分が自然と一体化していくような感覚を味わった。夜が明ける瞬間、暖かい陽射し、遥かに連なる山々。自分が今いるこの場所が、日常から遠く離れた世界であることに、妙な高揚感を覚えた。
装備と補給の工夫(前半)
食料・水・レイヤリングといった面では、軽量化を意識しながらも無理をしない構成を心がけた。基本は「無理のないスピードで歩くこと」。それによって、水分の消費も抑えられるし、食料も過不足なく計画できる。 水場の区間によって必要量は変わるが、1Lで十分な人もいれば、2Lでも足りない人もいる。たくさん持てば安心だが、水はとにかく重たい。必要な量は経験や行程から判断するしかないが、5月前半であれば、多くの人にとっては2L以下でも十分なケースが多いと思う。
ウェアはパフォーマンスを最優先に考えた。レインウェアは軽量性と撥水耐久性のバランスが良いfinetrack製を使用。リニューアル後のモデルは機能面でも優れており、デザインもシンプルで着やすい。レインパンツはTrail Bum。ワタリ幅が広めなので、ロングパンツの上からでも履きやすく、ポケットの位置も絶妙。非常に使いやすかった。走らない山行ではこのパンツをメインに使用している。

ショートパンツも用意していたが、今回は出番なし。履いていたのはTeton Bros.のスクランブリングパンツで、このパンツの安心感は本当に素晴らしい。生地は薄く風通しが良いのに、岩場で擦れても破れにくい。細身のシルエットで足さばきも軽やか。暑さを理由にショーツを選ぶ人も多いが、このパンツであれば暑さはほとんど気にならなかった。

標高2,000m近い稜線と、0mに近い里との気温差に対応できるよう、トップスは細かくレイヤリングできる構成にした。ベースにIcebreakerのメッシュ地ウールタンクトップ、次にmilestoneのフーディ、そしてRIDGEのアルファフーディとTilakのウィンドシェル。気温や風に合わせて1枚から3枚までを柔軟に重ねる。よく「フードが渋滞する」と言われるが、実際はどれも活躍した。風・気温・行動量に応じて調整でき、それぞれのフードが確実に機能した。

装備と補給の工夫(後半)
シューズはメレルの MTL LONG SKY 2 を使用。現在市販されているトレランシューズの中でも、群を抜いて乾きが早い。水の抜けが良く、乾きも速いため、濡れても不快感が少ない。ソールはやや薄めで路面との一体感があり、アッパーも破れにくく安心感がある。

靴下は合計5足を持参し、すべて使用した。これがなければ途中で撤退していたかもしれない。行程の7割は雨の中で、靴は常に濡れていた。足裏のトラブルは気合ではどうにもならない。靴下を定期的に交換し、足をリセットすることが継続のカギだった。
手袋は保温性だけでなく、鎖場や木を掴む際、あるいは転倒時のケガ防止のためにも必須。防水ではないが、乾きが速く安心して使える。濡れても気にならないというのは、精神的にも大きい。

ザックはSAMAYAの Ultra Pace。身体にぴったりとフィットし、揺れが少ない。まるで体の一部になったような安定感がある。生地にはダイニーマが使われており、縫い目にはシーム処理がされているため、内部に水が入ってくるようなことはない。シームの劣化リスクはあるものの、防水性は非常に高く、今回のような悪天候でも安心して使えた。

ヘッドランプは milestone の mi-i1。明るさ、バッテリー持続時間、色温度など、全体のバランスが非常に良い。夜間行動を前提にするなら、この装備は必須だと改めて感じた。

この道を歩こうとする人へ
山を歩く人なら、一度は通しで歩いてみたいと思う道。それが大峯奥駈道だ。人生を豊かにしてくれる、かけがえのない体験になるはずだ。ただし、体力・スキル・計画、それぞれに対して十分な準備が必要だと思う。
今回のチャレンジは、一般的には無謀に見えるかもしれない。しかし自分としては、余裕を持って行動できたし、無理をした覚えもない。翌日は多少足の重さは感じたが、筋肉痛などはない。
人によっては5〜6泊しても余裕がない場合もあるし、一方で20時間を切って走破できる人もいる。 大切なのは、自分の体力や技術レベルに合わせて日程を設定すること。そして、どんなスタイルであっても平均以上の体力は必要になると思う。
スルーハイクを目指すなら、日頃からジョギングなどで基礎体力を維持し、ある程度の荷物を背負って山を上下するトレーニングもしておくと良い。また、クライミングジムなどで三点支持の基本を体に染み込ませておくのもおすすめだ。 装備の選定も重要だ。軽量化にこだわりすぎても、逆に荷物を詰め込みすぎても良くない。自分に合ったバランスを見つけることが必要だろう。ただ、そのためにいろいろと考えたり、準備を重ねたりする時間こそが、すでにこの道の一部なのだと思う。
使用したアイテム一覧

エバーブレスフォトンジャケット (MEN'S)
長時間の雨でも安心の1枚。ベンチレーションが効いている。単色で使いやすい。

WALKER SHELL PANT
非常に優秀なレインパンツ。ハイキングに使いやすい特徴を備えている。

SCRAMBLING PANT (Men)
素早く動ける、通気性が高い、生地が強い、超軽量。アクティブに動くにはコレしかない。

Alpha Full Zip Hoodie
一年中活躍するアルファ。特に春から秋にかけては必需品。ダブルジップが使いやすい。

MTL LONG SKY 2 MATRYX®
これほどまでに軽くて、通気性が高くて、丈夫で、走りやすいシューズはない。濡れた斜面を下る時も扱いやすい。

ラピッドラッシュグローブ
finetrackのアイテムには常に助けられています。

ULTRA PACE
圧倒的な一体感。値段相応の価値があります。ここぞという時に使用するザック。スタイルも完璧。

MS-i1 “Endurance Model”
これなしでは夜の闇に安心して向かっていけない。トレイルランナーだけでなく、アクティブに動くハイカーにも。